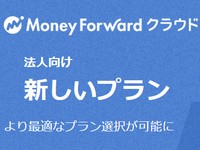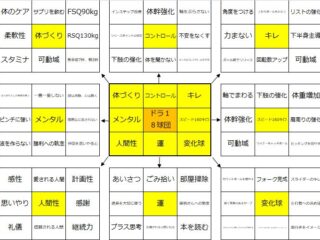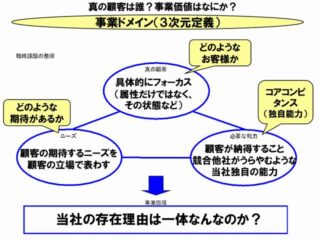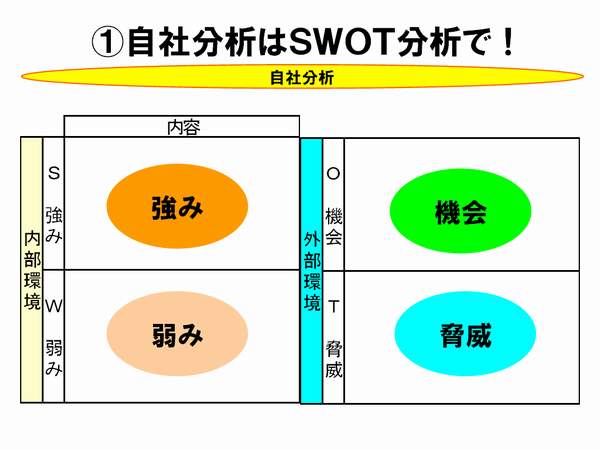経営戦略
経営戦略 経営計画、発表だけで終わっていませんか?現場が主役になる会議の進め方(経営計画発表会後にグループディスカッションを実施)
8月12日、ある企業様の経営計画発表会で、第二部の意見交換会の進行役(ファシリテーター)を務めさせていただきました。素晴らしい計画が発表された後、その熱量をどうやって実際の現場で「次の一歩」につなげるか。これは多くの中小企業が抱える共通の課題ではないでしょうか。今回は、計画を"絵に描いた餅"で終わらせず、社員みんなが「自分ごと」として動き出すための会議の進め方について、当日の様子を交えながらご紹介...