 ある企業では社員同士の連絡や会社からの業務連絡に、私用で使用しているLINEを使っていました。しかし、LINEのような私的利用を主目的としたチャットツールを業務で使用することには、情報管理やセキュリティの観点から問題があります。そこで検討の結果、業務用のコミュニケーションツールとして「Chatwork」を採用することとし、まずは試験的に導入してみました。その際、Chatworkはパソコンでの利用よりも、各自のスマートフォンにインストールして利用する方が、連絡の迅速性や利便性が高いという結果が得られました。
ある企業では社員同士の連絡や会社からの業務連絡に、私用で使用しているLINEを使っていました。しかし、LINEのような私的利用を主目的としたチャットツールを業務で使用することには、情報管理やセキュリティの観点から問題があります。そこで検討の結果、業務用のコミュニケーションツールとして「Chatwork」を採用することとし、まずは試験的に導入してみました。その際、Chatworkはパソコンでの利用よりも、各自のスマートフォンにインストールして利用する方が、連絡の迅速性や利便性が高いという結果が得られました。
試験運用の経過も良好だったため、今後は正式にスマホでChatwork業務利用を開始することになりました。そこで、正式に以下のような制度化を進めることにしました。このようなこともDX化のひとつです。
社員のスマホを業務利用する「BYOD」導入

社員のスマホを業務で使うのは「BYOD」という制度です
この中小企業では社内の連絡手段としてChatworkを導入しました。当初は試験的な導入でしたが、外出先でもスムーズな連絡が取れるようになったことで、業務の効率が大幅に向上。社員からは「スマホ一台でどこでも連絡がとれて仕事が進む」と好評でした。
しかし一方で、「私物のスマートフォンを業務で使うのに、通信料の負担が気になる」という声も出てきました。
そこで会社は、月額1,000円の「通信手当」を支給する制度を設け、あわせて業務利用のルールも明文化することにしました。
現在では、個人のスマホを業務で使うというBYOD(ビーワイオーディ:Bring Your Own Device)を正式な制度として運用しています。
この例では、BYOD導入をコスト削減や業務効率化につなげる一方、社員の負担軽減と明確なルールづくりをすることで定着化することが狙いです。
BYOD導入の主なメリット
1. コスト削減
企業がスマートフォンや携帯電話を支給する必要がなくなり、初期費用や月々の通信料を大幅に削減できます。
2. 業務の迅速化
社員が普段使っている端末で、場所を問わず連絡や情報アクセスが可能になります。特に外回りやテレワークが多い職種では、即時対応ができる体制は大きな強みです。
3. 社員の利便性・業務効率の向上
慣れた操作環境での業務が可能になるため、入力ミスや戸惑いが減り、ストレスも軽減されます。
想定される課題とリスク
1. 情報漏洩のリスク
私物端末の紛失・盗難時に、企業の業務データが流出する恐れがあります。特に退職後もアプリが残っていると情報が残る可能性があります。
2. 私用との境界が曖昧に
仕事用の通知が私的な時間にも届くようになり、プライベートを圧迫する恐れもあります。
3. IT管理の負担増
スマートフォンの機種やOSが社員ごとに異なるため、アプリの互換性や設定の確認作業が煩雑になる場合があります。
安心してBYODを導入するための4つの対策

1. MDM(モバイルデバイス管理)の活用
業務アプリやデータを遠隔で管理できるようにし、紛失時には「リモートワイプ(遠隔消去)」で情報漏洩を防ぎます。
2. 業務専用アプリの導入
ChatworkやSlack、Gmailなど、業務専用アカウントを設定することで、私用と業務の使い分けが明確になります。
3. 利用ルールの明文化
たとえば「勤務時間外の業務連絡は原則禁止」「業務用アプリにはパスコードロック必須」など、ルールをしっかり定めて周知します。
4. 定期的な研修・点検の実施
セキュリティ教育や利用マナーに関する研修を継続的に行い、社員全体の意識向上を図ります。
導入時のポイントと手当の工夫
-
試験運用からスタートする
いきなり全社導入ではなく、小規模な部署から試して運用課題を洗い出しましょう。特に営業部門など、外出が多い部門から試験運用すると制度の定着がしやすいです。 -
通信手当などの補助制度を整備する
今回の企業事例のように、月1,000円程度の通信手当を支給することで、社員の納得感や公平性が保てます。
なお、個人の端末をもっと業務で頻繁に使うような場合は手当の増額も検討したほうがいいでしょう。スマホの業務利用には1000~3000円というのが中小企業で妥当な範囲と考えられます。
【スマートフォン業務利用手当 運用マニュアル】
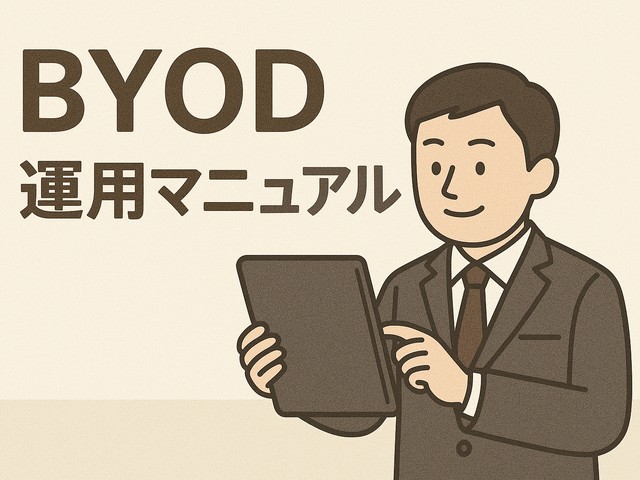
会社として正式にBYOD制度を導入するなら運用マニュアルを作成したほうがよいです。以下はサンプルですので自由に改変してお使いください。
第1章:制度概要
-
対象:業務上、個人のスマートフォンを継続的に利用している社員
-
支給額:月額 1,000円(税込)
-
支給方法:月次給与とともに支給
-
目的:通信料・端末利用にかかる個人負担の一部補助
第2章:運用フロー
1. 対象者の申請・承認
| ステップ | 担当者 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 社員本人 | 「スマートフォン業務利用同意書」を記入・提出 |
| ② | 所属上長 | 業務利用の必要性を確認し、同意書に承認サイン |
| ③ | 総務/人事 | 同意書を保管し、名簿に追加(Excel等で管理) |
| ④ | 経理 | 月次手当支給対象リストに基づき給与計算へ反映 |
第3章:手当の支給と管理
1. 支給処理
-
経理担当は毎月の給与処理時に対象者一覧を確認し、月額1,000円を加算。
-
支給は課税対象(給与所得)として取り扱います。
2. 台帳管理(例:Excelファイル)
| 社員名 | 部署 | 承認日 | 手当開始月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 営業部 | 2025/6/1 | 2025年7月 | Chatwork・電話利用 |
第4章:見直し・停止の対応
1. 見直しが必要なケース
-
業務利用が一時的または不要になった場合
-
社員の異動、休職、退職など
2. 停止手続き
-
所属長が停止理由を確認し、総務・経理に報告
-
対象リストから削除、次月より手当支給を停止
第5章:注意事項
-
スマートフォンの使用実態が不明確な場合は、手当支給を見合わせてください。
-
対象外の私用利用への補填とならないよう、業務利用の限定性を意識してください。
-
セキュリティ対策(パスコード・紛失時の連絡義務など)は同意書で本人に確認済みとします。
制度規程:スマートフォン業務利用手当制度

スマートフォン業務利用手当制度
第1条(目的)
この制度は、社員が自己所有のスマートフォンを業務に利用する場合における、通信費等の実費負担に対して、会社が適正な手当を支給することを目的とします。
第2条(対象者)
スマートフォンを業務に使用し、かつ上司の承認を受けた社員を対象とします。
第3条(支給金額)
業務利用者には、月額1,000円(税込)の手当を支給します。
※手当の金額は利用頻度の多さや物価上昇などによって見直す必要があります
第4条(支給方法)
手当は毎月の給与に加算して支給します。
第5条(手当の見直し・停止)
次のいずれかに該当する場合は、手当の見直しまたは停止を行います。
-
業務利用の必要性がなくなった場合
-
不正利用やルール違反があった場合
-
本人が希望した場合
【社内通知文:スマートフォン業務利用手当制度について
社員各位
業務の円滑な遂行およびコミュニケーションの効率化を図るため、社員が自己のスマートフォンを業務に利用する場合において、下記のとおり手当を支給する制度を導入いたします。
【制度概要】
・対象:業務上スマートフォンを使用している社員(承認制)
・内容:月額1,000円の定額手当を支給
・支給開始:〇年〇月分給与より
・備考:手当を希望される方は、別紙「業務利用同意書」をご提出ください。
今後も、業務効率化と働きやすい環境づくりに努めてまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇
スマートフォン業務利用同意書
私は、自己所有のスマートフォンを会社業務に使用することについて、下記内容に同意いたします。
-
使用目的は業務上の連絡(電話、メール、Chatwork等)に限定します。
-
スマートフォンには適切なセキュリティ設定(パスコードロック等)を施します。
-
業務利用に対し、会社より月額1,000円の手当が支給されることを確認します。
-
退職・業務内容の変更などにより業務利用が不要となった場合は速やかに会社に報告します。
氏名(署名):
所属部署:
日付: 年 月 日
※運用のためのマニュアルや制度のテンプレートはサンプルですので、自由に改変してご利用ください。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】
記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。
本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,870 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。
遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。
facebook https://www.facebook.com/tohdamikio
ツイッター https://twitter.com/tohdamikio
LINE https://lin.ee/igN7saM
チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda
また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。
※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)
※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)
株式会社ドモドモコーポレーション
石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171
電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)
IP電話:050-3578-5060(留守録あり)
問合→メールフォームからお願いします
法人番号 9220001017731
適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731


