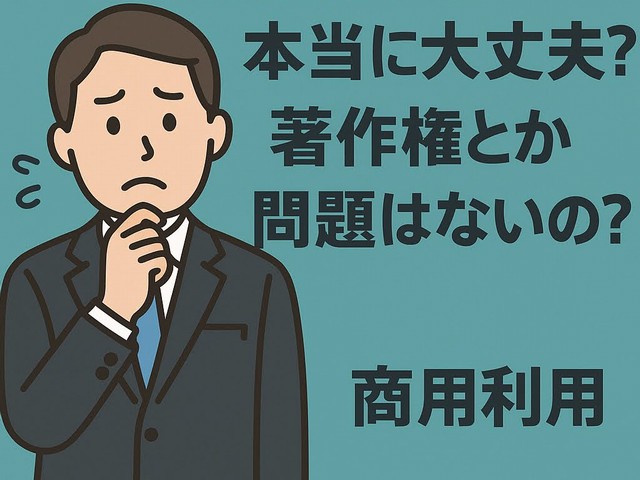 生成AIの進化は目覚ましく、ビジネスに活用したいと考える方が増えています。しかし、「AIが作った文章や画像を、会社のホームページや広告(商用利用)に使って、著作権法などの問題はないか?」という不安の声も多く聞かれます。この「AIと知的財産権」の問題をスッキリ解説します。
生成AIの進化は目覚ましく、ビジネスに活用したいと考える方が増えています。しかし、「AIが作った文章や画像を、会社のホームページや広告(商用利用)に使って、著作権法などの問題はないか?」という不安の声も多く聞かれます。この「AIと知的財産権」の問題をスッキリ解説します。
【結論】AIの商用利用は「基本OK」、ただし「重大な例外」あり
まず結論です。ChatGPT(OpenAI社)やGemini(Google社)は、利用規約上、生成したコンテンツの「商用利用」を原則許可しています。無料版でも同様です。
生成AIの商用利用、注意点を解説します
基本的に商用利用はOKですがサービス提供側のルールに注目

ChatGPT(OpenAI社)とGemini(Google社)は、生成したコンテンツの「商用利用」を原則許可しています。おおむねAIサービスを提供している他社も同様です。
しかし、重大な例外があります。それは「無料版 Microsoft Copilot(旧 Bing Image Creator)で生成した画像」です。
Microsoftの個人向け規約では、Copilotで生成した画像は「非商用(商用利用不可)」に限定されていると解釈するのが最も安全です。
「AIエンジン(DALL-E 3)はChatGPT Plusと同じでは?」と思うかもしれませんが、「どのサービスを経由したか」でルールが変わります。
- OpenAI(ChatGPT Plus)経由 → 商用利用OK
- Microsoft(無料Copilot)経由 → 商用利用NG
これは提供する側のルールなので、我々利用者としては遵守するしかありません。本当に要注意です。このことを誤ると規約違反のリスクがあるため、AI利用で最も注意すべき点の一つです。
【安全に使うための2大リスクと解決策】

「Copilot画像」以外なら安心かというと、そうではありません。AIをビジネスで使うには、大きく2つのリスクを理解し、対策を講じる必要があります。
リスク1:機密情報の「学習」と「漏洩」
無料版や個人向け有料版のAIは、入力した情報をAIの「学習」に使う可能性があります。もし社外秘の顧客リストや新商品企画を入力すれば、その情報が将来、他人の回答に含まれて漏洩するリスクがゼロではありません。
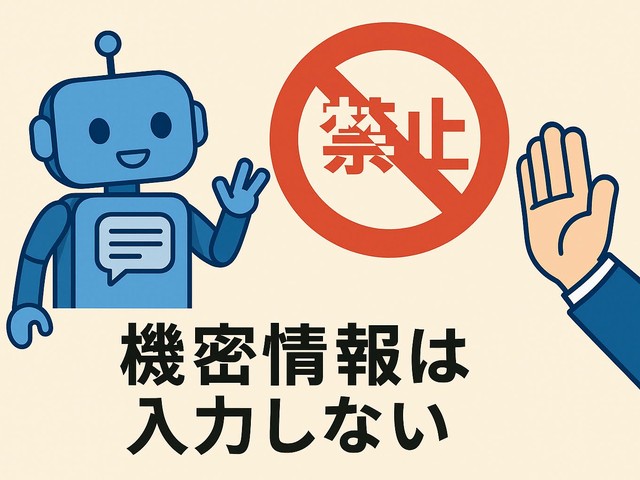
対策:
-
- 機密情報は絶対に入力しないこと。
- 個人向け有料版(ChatGPT Plus等)は、学習を拒否する「オプトアウト設定」を必ず行うこと。
- 最も安全なのは、入力データを学習に利用しないと規約で保証されている「企業向けプラン(Copilot for Microsoft 365、ChatGPT Team、GoogleWorkspace等)」を契約することです。企業向けプランは有料ですが、安全を購入しているようなものかもしれません。
リスク2:「著作権」をめぐる問題
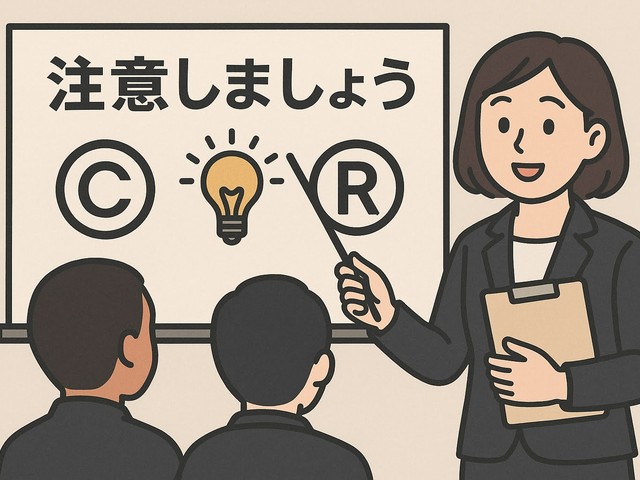
AIの商用利用には、2種類の著作権リスクが伴います。
- 他人の著作権を「侵害」するリスク AIは膨大なデータを学習しているため、生成物が既存の作品(文章、イラスト、ロゴ)と偶然そっくりになり、意図せず「盗作」や「著作権侵害」になってしまう可能性があります。責任を負うのはAIではなく、それを利用した「あなた(会社)」です。
- 自分の「著作権」が「発生しない」リスク AIが自動生成しただけの文章や画像は、「人間の創作的な関与」が少ないと見なされ、著作権が発生しない可能性が高いです。これは、競合他社にあなたのコンテンツを丸パクリされても「著作権侵害だ」と主張できないリスクを意味します。

対策:
- AIの生成物は「下書き」と心得る。 AIの生成物をそのまま使わず、必ず「人間」がファクトチェック、編集、加筆修正を行います。独自の表現や具体例を加えることで、「人間の創作的な寄与」が生まれ、上記2つの著作権リスクを同時に軽減できます。
- 画像利用は規約を厳守する。 前述の通り、無料Copilotの画像は商用利用を避けます。ビジネスで安心して使うなら、ChatGPT Plus、Adobe Firefly、または企業向けプラン(Copilot for Microsoft 365)など、「商用利用が許可」され、できれば「著作権補償」が付いているサービスを選びましょう。
- プロンプト(指示)を工夫する。 「〇〇(作家名)風に」「〇〇(作品名)に似せて」といった指示は、著作権侵害リスクを高めるため避けるべきです。
AIを「賢い部下」として使いこなそう
生成AIは、正しく使えばビジネスの強力な武器になります。 「商用利用OK」の言葉をうのみにせず、
- サービスごとのルール(特に無料Copilot画像は商用NG)
- 情報漏洩リスク(機密情報は入力しない)
- 著作権リスク(他人の侵害、自分の権利不発生)
これらを理解し、AIに丸投げせず「人間が仕上げる」ことを徹底すれば、AIは最強のビジネスパートナーとなります。リスクを恐れず、賢く活用していきましょう。
自社の生成AI利用ガイドラインを作成し遵守しましょう

企業が「生成AI利用ガイドライン」を策定し、全社で遵守することは、「リスクの回避」と「安全な活用の促進」という両面から非常に重要です。
1. 「守り」:重大なリスクから会社を守るため
生成AIには、便利な反面、大きなリスクが潜んでいます。
- 情報漏洩リスク: 社外秘の機密情報や顧客の個人情報をAIに入力すると、それがAIの学習データに使われ、外部に漏洩する恐れがあります。
- 著作権侵害リスク: AIが生成した文章や画像が、意図せず他人の著作物と酷似・盗用してしまい、法的なトラブルに発展する可能性があります。
- 信用失墜リスク: AIは平気で嘘(ハルシネーション)をつくため、生成された情報を鵜呑みにして誤った情報を発信すれば、会社の信用を大きく損ないます。
ガイドラインは、これらのリスクを全社員が正しく認識し、「入力してはいけない情報」や「生成物の確認義務」といった最低限のルールを定めることで、会社を法務・セキュリティ上の重大な事故から守る「防波堤」の役割を果たします。
2. 「攻め」:AI活用による生産性向上を促進するため
リスクばかりを恐れてAIの利用を禁止すると、業務効率化のチャンスを逃し、競合他社に遅れをとってしまいます。
ガイドラインによって「やって良いこと」と「悪いこと」の境界線が明確になれば、社員は「これは使って大丈夫か?」と迷うことなく、安心してAIを業務に取り入れることができます。
ルールを整備することは、社員の積極的なAI活用を後押しし、組織全体の生産性を向上させる「アクセル」を踏むためにも必要なのです。
生成AI利用ガイドラインを作成しましょう
ガイドラインの策定と周知徹底は、AIという強力なツールの危険な側面をコントロールしつつ、その恩恵を最大限に引き出すための「安全装置(ブレーキ)」と「羅針盤(アクセル)」を全社で共有する行為です。企業の競争力と社会的信頼を守るために、今や不可欠な取り組みとなっています。
まだ生成AIガイドラインを作成していない企業はぜひ作成し、社内に周知したうえで遵守していきましょう。
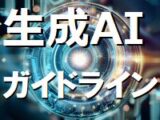

関連記事もご覧になってみてください。
生成AIの商用利用や知財に関する出典元情報
生成AIの商用利用や知財に関して調べた出典元情報について以下に紹介しておきます。
1. Microsoft Copilot(無料版)の利用規約について
無料版 Copilot(旧 Bing Image Creator を含む)の利用は、Microsoft の一般的なサービス規約に基づき、「個人的・非商用」利用に限定されると解釈されています。
- 出典タイトル: Microsoft サービス規約
- リンク:
https://www.microsoft.com/ja-jp/servicesagreement/ - 該当箇所(の解釈): この包括的な規約の「サービスの使用」セクションなどにおいて、特に別途の商用ライセンスが提供されない限り、コンシューマー(個人)向けサービスは「お客様個人の非商業的(商業的でない)使用を目的」として提供される、という基本方針が示されています。無料版 Copilot の画像生成は、この一般規約が適用されると解釈するのが最も安全です。
2. OpenAI (ChatGPT) の商用利用について
OpenAI は、利用規約において、ユーザーが生成したコンテンツ(アウトプット)の権利をユーザーに譲渡し、商用利用を許可しています。
- 出典タイトル: OpenAI 利用規約 (OpenAI Terms of Use)
- リンク:
https://openai.com/policies/terms-of-use - 該当箇所: 「3. Content」セクション。(a)項でユーザーが入力(Input)に対する権利を保持すること、(b)項で「OpenAIは、本規約の遵守を条件として、アウトプット(Output)に関するすべての権利、権原、利益をユーザーに譲渡します」と記載されており、これにより商用利用が可能となっています。
3. Copilot for Microsoft 365(企業向け)の保護について
企業向け有料プランでは、「商用データ保護」と「著作権補償」が明確に提供されています。
- 出典タイトル: Microsoft 365 Copilot のデータ、プライバシー、セキュリティ
- リンク:
https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy - 内容: 企業向け Copilot (Copilot for Microsoft 365) が、「商用データ保護 (Commercial Data Protection)」の対象であることを示す公式ドキュメントです。お客様のデータ(プロンプトや応答など)が Microsoft 365 サービスの境界内に留まり、AI モデルのトレーニング(学習)には使用されないことが明記されています。
- 出典タイトル: マイクロソフト、お客様向けの Copilot Copyright Commitment を発表 (Microsoft announces new Copilot Copyright Commitment for customers)
- リンク:
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2023/09/07/copilot-copyright-commitment-ai-legal-concerns/(元記事:英語) - 内容: Microsoft の公式ブログ記事です。有料の法人向け Copilot サービスおよび Azure OpenAI Service の利用者が、生成物の出力結果によって第三者から著作権侵害で訴えられた場合、Microsoft がその顧客を防御し、不利な判決や和解にかかる費用を支払う(=補償する)ことを発表しています。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】
記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。
本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,876 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。
遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。
facebook https://www.facebook.com/tohdamikio
ツイッター https://twitter.com/tohdamikio
LINE https://lin.ee/igN7saM
チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda
また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。
※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)
※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)
株式会社ドモドモコーポレーション
石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171
電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)
IP電話:050-3578-5060(留守録あり)
問合→メールフォームからお願いします
法人番号 9220001017731
適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731


